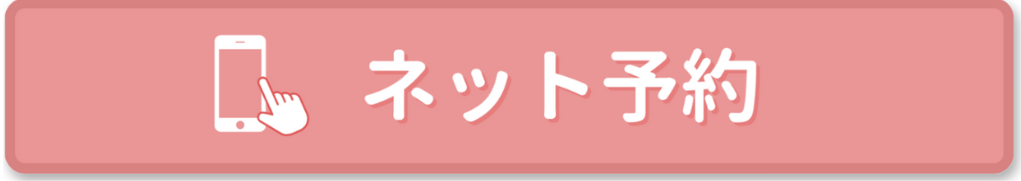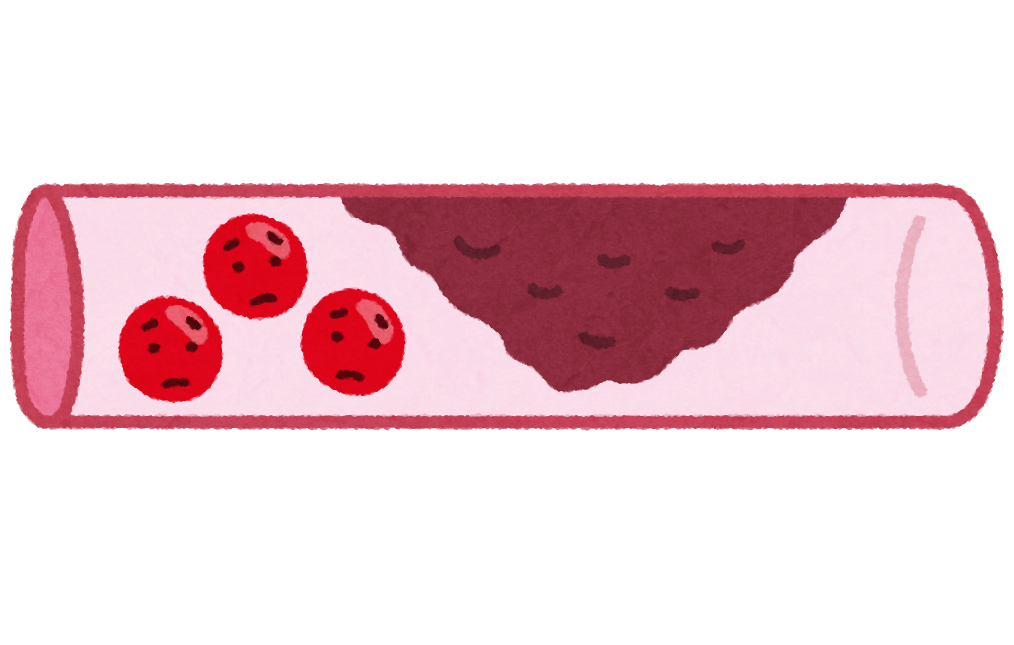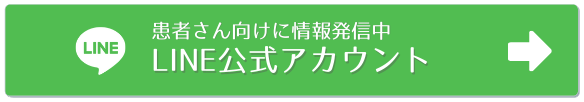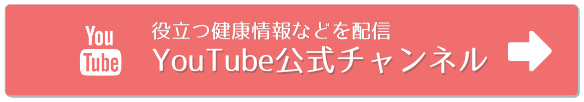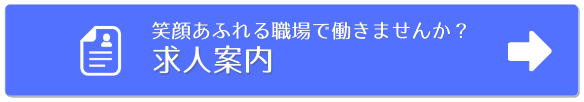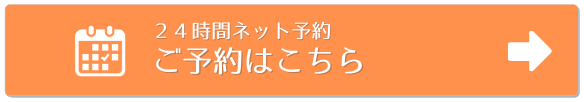目次
足の血管が詰まる直前のSOSサイン4選

歩いていると足が痺れて、痛い・・・
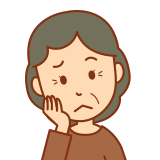
1ヶ月前にできた足の傷がなかなか治らない・・・
こんな症状に悩んでいる方は、今回のブログがきっと役に立つと思います。

みなさんこんにちは!あまが台ファミリークリニック院長の細田です。
今回は、脚の血管が詰まり、
動脈硬化を起こしてしまう恐ろしい病気についてまとめました。
ブログを見ることで、ご自身やご家族、大切な方がの寿命を
縮めないきっかけになるかもしれません!
最後に脚の動脈硬化の予防法もお伝えしますので、
ぜひ最後までご覧ください!
足の血管が詰まる病気とは?
動脈硬化で血管が詰まってしまう病気と言えば、皆さんはまず何を思い浮かべるでしょうか。
心筋梗塞や脳梗塞が代表的ですが、今回のテーマであるもう一つの病気は、
私たちの寿命を縮めないために絶対に知って欲しい病気です。
これは何の病気でしょうか?
ズバリ!足の血管が詰まる病気です。
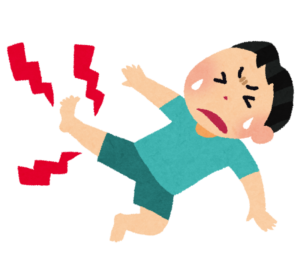
足の動脈硬化とは?
正式な病名は末梢動脈疾患(PAD)で、今回は分かりやすいように「足の動脈硬化」と呼びます。
心筋梗塞や脳梗塞と並んで重大な病気だと覚えておいてください。
足は「第2の心臓」と言われるぐらいですが、足の動脈硬化が進み血液がいかなくなると、
最悪足の切断ということにもなりかねません。

足の切断!?先生、ちょっと大げさじゃないですか?

足の動脈硬化ぐらいで死ぬわけじゃないですよね。

そう思う方もいるかもしれませんが、
この足の動脈硬化を侮ってはいけません!!!
ある研究では、足の動脈硬化がかなり進んだ場合の5年間の死亡率は、
大腸がんや乳がんよりも高かったという報告があります。
また、足の動脈硬化があると、
5年間での死亡率は30%と驚くべき数字もあり、本当に侮れないのです。
ということで、今回の内容は、
- 足の動脈硬化のSOSサイン4つ
- 足の動脈硬化をいち早く見つける、簡単なチェック方法
をご紹介します!!
知らないと怖い 足の血管が詰まる直前のSOSサイン4選
足の血管というのは心臓から最も遠い位置にありますので、
足の動脈硬化の症状は足の指先から出ることが多いです。
足の血管の血流が悪くなると、細胞に酸素や栄養がいかなくなりますから、
さまざまな症状が出てきます。
足の血管が詰まる直前の症状を4つ説明していきます。
1つ目、2つ目、3つ目、4つ目と、数字が大きくなるほど動脈硬化も進行し重症だと思ってください。
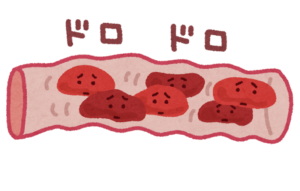
1.足のしびれ
クリニックには足の冷えを訴える患者が多く、
もともと体質的に冷え性の方と足の動脈硬化由来の冷えは、ある程度区別が可能です。
体質的な冷え性の人は、若い頃から特に冬に冷えを感じることが多く、
デスクワークなどで運動不足の傾向があります。
一方、足の動脈硬化による冷えは
であることが多く、
などの生活習慣病を併せ持っているケースが多い のも特徴です。
この場合、冷えだけでなく ジンジン・ピリピリとしたしびれ が現れることがあり、
進行すると 感覚が鈍くなり傷にも気づかなくなる ことがあります。
2.間欠性跛行(かんけつせいはこう)
簡単に言うと、
歩くとふくらはぎや太ももがしびれるので休み休み歩かないといけない状態です。
数分歩くだけで足のしびれや痛みを感じ、こむら返りを自覚する方もいます。
そして、10分くらい休むと症状が良くなりまた歩けるようになるというのが
典型的なパターンです。
・歩行時に筋肉が酸素を必要とするが、血管が詰まっているため
十分な血液が届かず、痛みが発生する
この間欠性跛行(かんけつせいはこう)と間違えやすい病気が2つあります。
歩いていて膝だけが痛い場合、足の動脈硬化は関係ないことが多いです。
特に多いのが「変形性膝関節症」という病気で、
膝の関節の軟骨がすり減ることで痛みが生じます。
膝が痛い原因の多くはこの病気なので、混同しないよう注意しましょう。

この病気は、脊髄の神経が圧迫されることで腰が痛くなり、足がしびれるのが特徴です。
歩き続けると足のしびれや痛みで歩けなくなる点が、
足の動脈硬化による間欠性跛行と非常に似ています。
しかし、この2つの病気は治療法が異なるため、正しく見分けることが大切です。
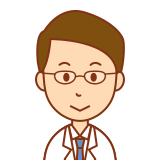
腰部脊柱管狭窄症と脚の動脈硬化の
簡単な見分け方をお伝えします。
腰部脊柱管狭窄症の場合は、
前かがみの姿勢や自転車をこぐと痛みが和らぐのが特徴です。
一方、足の動脈硬化による痛みは姿勢に関係なく続くことが多いです。
整形外科を受診して検査すればすぐに分かる病気ですから、
疑わしい場合は受診するといいと思います。
ただし気をつけないといけないのが、足の動脈硬化がある人は、
腰の神経を圧迫されている病気を併せ持っているケースも多々あります。
その場合は、循環器内科と整形外科の両方を受診するのが良いと思います。
3.安静時の痛み
2つ目の症状、間欠性跛行よりもさらに足の動脈硬化が進むと、
横になって安静にしていても足に酸素や栄養が供給できないため、
足に痛みが出ることがあります。

もう少し具体的に説明すると、この3段階目に進むと、
日中は痛みを感じにくいのですが、横になって
心臓と同じ高さになった時に痛みが感じやすくなるのです。
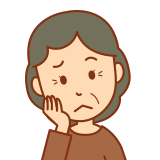
どうして心臓と同じ高さになると痛むの?

理由は、立っている時は重力が後押しして、
ある程度血流が保たれます。
しかし、心臓と同じ高さになると、重力の助けがなくなり、
足への血流がいかなくなって痛みが出るのです!

安静にしていても痛いというのはよほど動脈硬化が進んでいる
SOSサインですから、足の切断に至らないためにも
すぐに医療機関を受診してください。
ここで足の動脈硬化の治療について簡単にご説明します。
1段階目の足の血管が詰まる直前の症状、
1つ目は冷えやしびれでしたね。
2つ目は間欠性跛行、休み休みじゃないと歩けないという症状でしたね。
この第1段階、第2段階の場合は血液をサラサラにする薬を使ったり、
血糖値が高い方や血圧が高い方には生活習慣病の治療を行ったり、
タバコを止めるようにお話しするわけですが、
今説明した3段階目の安静にしても痛いという状態の場合は、
バイパス手術と呼ばれる足の血管をつなぐ外科的手術が行われることもあります。
また、ステント治療と呼ばれる、
狭い血管のところで金属の網を風船のように外側に広げて血管を広くする治療
も行われます。
早期発見、早期治療が大切だということを繰り返し伝えたいと思います。
4.潰瘍(かいよう)と壊死(えし)
潰瘍とは、皮膚がただれるような傷を指します。
血流が極端に悪化し、酸素や栄養が足先まで届かなくなると
上の方から順番にえぐれていってしまいます。
また、壊死とは組織が完全に腐って死んでしまっている状態で、
ミイラ化して干からびて黒くなっている状態です。
このような状態になると細菌がつきやすくなり、
感染症で命を落とすということも心配されます。
最悪の場合は、足の切断を余儀なくされる場合もあります。

自宅でできる動脈硬化の簡単なチェック方法
ここまでのお話を聞くと、

脚の動脈硬化が進んでいたらどうしよう
と不安になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

ここでみなさんに、
自宅でできる動脈硬化のチェック方法をご紹介いたします。

この画面を読みながらいくつかの方法を一緒にやってみましょう!
指先で足の表面を点検
では、指先で足の表面を点検したいと思います。足の表面には動脈があります。
足の甲の動脈を触ってみましょう
- まず、親指の骨を探します。
- 親指の骨から足首に向かって少しずつ指を動かします。
- やや人差し指側にずらして触れると、動脈の拍動(ドックンドックン)を
感じられる部分があります。
3本の指を当てると、ドックンドックンと拍動を感じるのですが、
足の動脈硬化で血流が悪くなっていると、拍動を感じられない、
あるいは弱い状態になっています。
また、右足はちゃんと触れるけれども、左足は触れないということもあります。
この場合、左足の動脈硬化がかなり進行していると考えられます。
🚨注意点🚨
このチェック方法は慣れないとすぐに触れることができない場合もありますので、
触れないからといってすぐに足の動脈硬化があると決めつけることはできません。
迷った場合は、すぐに主治医に相談するのが賢明です。
後脛骨動脈の確認
もう1つ確認したいのは、後脛骨動脈という足の動脈です。
これは右足の足の裏になりますが、人差し指があるところで、
右足の内側のくるぶしの下にもう1本血管があります。
ここに動脈が触れているかどうかを探ります。
触れる時に力を入れすぎると血管が逆に閉じてしまって触れづらくなりますので、
ある程度押しながらこの辺を反らし気味に触っていくと、
ドックンドックンと拍動を感じることができます。
日々のチェックの重要性
毎日やっているうちに触れるようになってきますので、
ぜひ自分自身の体を観察するためにとても大事なことなので、
頭の片隅に置いておいて、やってみてください。

今日お話ししたSOSサインのどれか1つがあれば
必ず医療機関で検査を受けていただきたいと思います。
とっても恐ろしい足の動脈硬化、どんな人に起こりやすいの?
この、脚の動脈硬化ですが、どの様な人にリスクが高いのでしょうか?
ご自身が当てはまるかどうか当てはめながら読んでみてください。
★70歳以上男性
70歳以上の2~5%の人に見られ、
男女比で言うと男性の方が女性よりも2倍かかりやすい
と言われています。
★喫煙
タバコを吸う人は吸わない人に比べてなんと3.8倍も足の動脈硬化が
起こりやすいという 研究結果もあります。
※ただし、20年以上禁煙した方は、タバコを吸わない人と同じぐらいに
足の動脈硬化になるリスクが下がると言われており、
できるだけ早く禁煙することが大切です。
★糖尿病
糖尿病を持つ方はそうでない方に対して3倍リスクが高いです。
糖尿病がある65歳以上の方になると、
100人中13人、つまり13%の方が足の動脈硬化を起こしているという
研究結果もあります。
★高血圧は2倍程度
★脂質異常症では1.5~2倍
と言われています。
今説明したリスク因子が1つよりも2つ、2つよりも3つある方は
なおさら注意が必要です。

ある患者さんの例をご紹介します。
私自身の外来に、72歳の男性の方が通院されており、
その患者さんは、タバコを吸い、高血圧があり、糖尿病がありました。

その方も2、3か月前から歩くと足がしびれると言って来院されていました。
整形外科を受診すると、「腰の病気ですね」と言って薬を出されたのですが、
なかなか良くならないので循環器内科を受診したところ、
重症な足の動脈硬化も併せ持っていることが判明しました。
受診の2ヶ月ぐらい前から足がしびれると言って来院されたのですが、
まだ潰瘍や壊死という状態には至っていなかったので、
ステント治療で無事に回復しました。
それでも、その後タバコをやめられずに痛みに悩んでいたことを覚えています。

ですから手術して治療したからいいのではなく、やはり予防が大事です。
では、最後に、足の動脈硬化を防ぐ方法についてお話しします。
脚の動脈硬化予防のポイント
は ①全身の動脈硬化を防ぐこと と ②フットケアを行うこと の2つです。
① 全身の動脈硬化を防ぐ
足の血管だけでなく、全身の血管が健康であることが大切です。
動脈硬化を進行させる原因には、タバコ、糖尿病、
脂質異常症(コレステロールの異常)などがあります。
そのため、次のことを意識しましょう。
★禁煙する
(タバコは血管を傷つけます)

★血圧・血糖値・コレステロールを管理する
(主治医と相談しながらコントロールしましょう)
★運動や食生活を改善する


場合によっては、医師の判断で薬による治療が必要になることもあります。

② フットケアを行う
もう1つ大切なのが、日常的な 足のケア です。
★足に傷がないか毎日チェックする
日頃から足に傷ができていないか確認し、
傷がそもそもできない状態を作ることが大切です。
特にかかとや指の間は注意して確認しましょう!

★傷ができにくい環境をつくる
足の動脈硬化がある方は、ちょっとした傷からバイ菌が入り、
致命的な感染症を引き起こすこともありますから、
家でも靴下を履いて感染を予防することが大切です。
また、靴はきつすぎたり緩すぎたりするものでなく、
足にフィットしたものを履くようにしてください。
靴擦れから感染が起こることもあります。

★乾燥を防ぎ、清潔を保つ
洗った後は水分をよく拭き取り、保湿をすることが大切です。


この方法は市販のハンドクリームでも良いですし、
医者に相談して、皮膚に浸透して保湿するお薬を塗るのも良いでしょう。
ただし、かかとにひびが入ってしまっていたり、
乾燥してかかとがカチカチになってしまっている場合には、
市販のクリームでも対応できないことがあります。
このような場合は、薬剤師さんやフットケアに詳しい看護師さん、
主治医の先生に相談して医薬品を処方してもらうのが賢明だと思います。

【まとめ】
それでは、今回のまとめです。
足の血管が詰まる前のSOSサイン4選
① 足の冷えやしびれ
最初のサインとして、足の冷えやしびれが現れます。
血流が悪くなることで、足先が冷たく感じたり、しびれが続くことがあります。
② 間欠性跛行(かんけつせいはこう)
歩くと足が痛くなり、休まないと歩き続けられない症状です。
ただし、この症状は 腰部脊柱管狭窄症(ようぶせきちゅうかんきょうさくしょう)とも
似ているため、放置するのは危険です。適切な診断を受けましょう。
③ 安静時の痛み
横になったときに足が痛む場合は、血流の低下が進行している可能性があります。
立っているときは重力で血流が流れますが、寝るとそれがなくなり、
痛みが強くなるのが特徴です。
④ 潰瘍や壊死(えし)
さらに進行すると、足に潰瘍(かいよう)や壊死が起こり、皮膚が黒く変色し、
最悪の場合は切断が必要になることもあります。
自宅でできる簡単チェック
以下の方法で、自分の足の状態を確認しましょう。
✅ 左右の足の温かさに違いがないか(つま先から足首に向かって触る)
✅ しびれや感覚の異常がないか
✅ 足の動脈の脈拍が触れるかどうか
違和感がある場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。
治療方法
初期段階 → 血液をサラサラにする薬や生活習慣の改善で進行を防ぐ
進行した場合 → バイパス手術(他の血管を使って血流を確保)や
ステント治療(血管内に金属の網を入れて広げる)を行う
足の動脈硬化がある方は、5年以内の死亡率が30%高く、
死亡原因の60%以上が 心筋梗塞や脳卒中 です。足の血管だけでなく、
全身の血管の健康を守ることが大切です。

今回は「足の血管が詰まる直前のSOSサイン4選」について
お話ししましたが、いかがでしたか?
気になる症状がありましたら、ぜひ当院までお気軽にご相談ください!