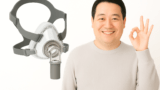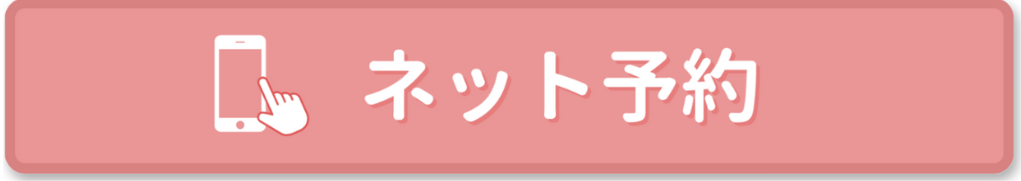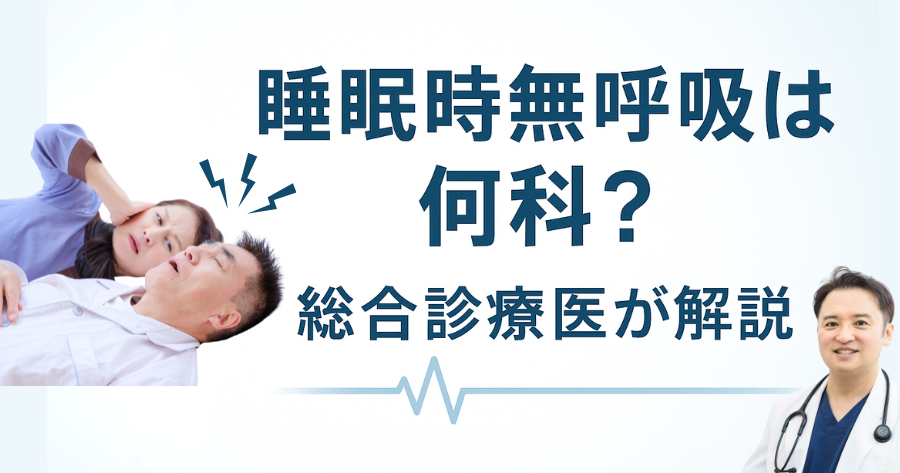「朝がしんどい」
「日中に眠くて集中できない」
──こうした症状で不安を感じる方がまず悩むのが、「どの科を受診すればいいのか?」という点です。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、呼吸だけでなく血圧・血糖値・体重など“全身の健康” と深く結びついているため、受診先で迷う方が非常に多い病気です。
この記事では、睡眠医療と生活習慣病の両方を専門的に診療している総合診療医の立場から、どこを受診すべきかをわかりやすく整理し、最後に「総合診療で診るメリット」もご紹介します。
睡眠時無呼吸症候群は何科を受診すべき?総合診療医がわかりやすく解説

こんにちは。
医療法人社団 緑晴会 あまが台ファミリークリニック 院長の 細田俊樹 です。
私はプライマリ・ケア(総合診療)を専門に25年。
睡眠時無呼吸症候群は年間1,500名以上、糖尿病は5,000名以上、肥満治療も年間数百件と、生活習慣病と睡眠医療の両面から総合的に診療しています。
(日本糖尿病学会正会員、日本睡眠学会所属)
「呼吸だけを見る」のではなく、「睡眠 × 生活習慣病 × 全身状態」をまとめて評価できるのが総合診療の強みです。
目次
睡眠時無呼吸症候群は「症状だけ」では診断できない理由

まず知っておいてほしいのは、睡眠時無呼吸症候群は症状だけでは正確な診断ができないということです。
いびきや日中の眠気は大切なヒントですが、「軽症・中等症・重症」を決めるには不十分です。

実際の診療では、「自分ではそこまでひどくないと思っていたのに、検査したら重症だった」という方もいれば、「眠気がつらいのに、検査では軽症だった」という方もいます。つまり、自覚症状と重症度は必ずしも一致しないのです。
そのため、まずは「睡眠中の呼吸を測る検査」に対応している医療機関かどうかを確認することが、最初の大切な一歩になります。
睡眠時無呼吸症候群を診ている主な5つの診療科
睡眠時無呼吸症候群は、原因や背景によって複数の診療科が関わる病気です。主に次の3つの診療科で診療が行われています(※2~4)。
睡眠時無呼吸症候群は何科を受診すべき?
診断には自宅で行う簡易検査、または精密検査(PSG)が必要です。
そのため、まずは検査を扱っている医療機関かを確認することが重要です。
1.かかりつけ医(一般内科)
クリニックによって異なりますが、睡眠時無呼吸症候群の検査や治療に対応している場合もあります。事前にホームページや電話で確認をしてから行くのが望ましいと思います。
2.呼吸器内科
呼吸の流れや気道の状態を専門的に診る診療科で、簡易検査や精密検査、CPAP導入まで対応可能な医療機関が多いです。
3.耳鼻咽喉科
鼻詰まり、扁桃肥大、アレルギー性鼻炎など “気道そのものの狭さ” が疑われる場合に適しています。

4.循環器内科
治療しても血圧が下がらない場合や心不全がある方は、睡眠時無呼吸の合併が疑われます。循環器内科で精査してもらい、必要に応じて睡眠検査へつなげます。

迷ったときはどうする?
受診先で迷ったら、下記3点を満たすところが安心です。
- 睡眠検査(簡易検査・精密検査)を扱っている。
- 治療(特にCPAP)までフォローできる。
- 生活習慣病も含めて診察できる。
これらに対応していれば、睡眠時無呼吸症候群の治療ができる医療機関と言えます。
生活習慣病がある方は「睡眠」と「全身」を一緒に診てもらうことが大切
全身をトータルで診ること
睡眠時無呼吸症候群は、「睡眠の病気」であると同時に、高血圧・糖尿病・肥満をはじめとした生活習慣病と密接に関わっています。私自身は、総合診療を専門にしていますが、高血圧、糖尿病、肥満治療を始め、様々な病気をトータルケアすることを心がけています。
- 無呼吸による酸素不足や覚醒 → 血圧が上がりやすくなる(※4)
- 睡眠の質の低下 → インスリンの効きが悪くなり血糖が上がりやすくなる(※5)
- 肥満 → のど周りに脂肪がつく → 気道が狭くなり無呼吸が悪化する(※6)

この「悪循環」を断ち切るには、睡眠だけでなく生活習慣病も含めて総合的に診ていくことがとても重要です。
当院では、
- 睡眠時無呼吸症候群:年間1,300人以上
- 糖尿病:年間5,000人以上
- 肥満治療:年間数百件
という診療実績があり、睡眠と生活習慣病の両面から診療できる体制を整えています。
「いびきもあるし、血圧や血糖も気になる…」という方は、どれか一つの病気だけを見るのではなく、まとめて相談できる医療機関を選ぶことが、長い目で見て大きな安心につながります。

それでも迷うときはどうする?受診先選びの3つのポイント
「一般内科・呼吸器内科・耳鼻科・循環器内科・総合診療科」どれも関係ありそうで余計に迷ってしまう…」という方も多いと思います。
そんなときは、次の3つのポイントで受診先を考えてみてください。
- 1.睡眠時無呼吸症候群の“検査”に対応しているか
- 2.検査だけでなく、その後の治療やフォローもしてくれるか
- 3.生活習慣病(高血圧・糖尿病・肥満など)も一緒に診てもらえるか
睡眠時無呼吸症候群の治療、とくに CPAP 治療は、始めて終わりではなく、継続的なフォローアップがとても重要だとされています(※7)。
そのため、「自宅や職場から通いやすい」「質問しやすい」「説明がわかりやすい」という点も、長く付き合う病気だからこそ大切なポイントです。

当院にご相談いただいた場合の流れ
当院にご相談いただいた場合、おおまかには次のような流れで診療を進めていきます。
- 問診で、いびき・眠気・生活習慣・既往歴(高血圧・糖尿病など)を丁寧に確認
- 自宅でできる簡易検査をご案内(指や鼻に小さな機械をつけて測定)
- 必要に応じて、精密検査(終夜睡眠ポリグラフ検査)をご紹介
- 検査結果にもとづき、CPAP などの治療が必要かどうかを判断
- 血圧・血糖・体重なども確認しながら、生活習慣病の管理も並行して行う
「自分が本当に無呼吸なのか知りたい」「検査の流れや費用が不安」といった段階から、丁寧に説明しながら一緒に進めていきますので、気になることは遠慮なくご相談ください。

まとめ:診療科名よりも「検査とフォロー」が大切です
睡眠時無呼吸症候群は、呼吸器内科・耳鼻科・循環器内科など複数の診療科が関わる病気です。どの診療科を受診するかで迷ってしまうのは、とても自然なことです。
ただ、実際に大切なのは、
- 睡眠中の呼吸を測る検査がきちんと行えるか
- 検査だけでなく治療や長期フォローも行ってくれるか
- 睡眠だけでなく生活習慣病も含めて総合的に診てもらえるか
という点です。
どこに行けば良いか悩んでいる方は、まずは相談しやすい医療機関に一度ご相談ください。
当院でも、睡眠時無呼吸症候群と生活習慣病の両面から、あなたに合った検査や治療方針をご提案いたします。
▼睡眠時無呼吸症候群の検査や治療の流れを詳しく知りたい方はこちら
当院の睡眠時無呼吸症候群の詳しいご案内ページ(
▼診察のご予約はこちら
あまが台ファミリークリニック 診療予約ページ
参考文献
- AASM Manual for the Scoring of Sleep and Associated Events. American Academy of Sleep Medicine(睡眠時無呼吸症候群の診断基準)
- 日本睡眠学会 睡眠時無呼吸症候群 診断・治療ガイドライン
- Li HY, et al. Otolaryngol Head Neck Surg. 耳鼻咽喉科領域における閉塞性睡眠時無呼吸の評価に関する研究
- Pedrosa RP, et al. Obstructive sleep apnea and resistant hypertension. Journal of Hypertension.
- Pamidi S, Tasali E. Obstructive sleep apnea and type 2 diabetes. Sleep Med Clin.
- Peppard PE, et al. Prospective study of the association between sleep-disordered breathing and hypertension. N Engl J Med.
- Weaver TE. Adherence to CPAP treatment and long-term follow-up. Sleep.
関連ブログ