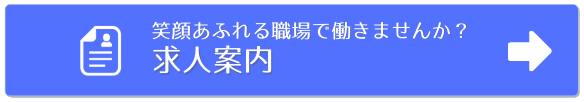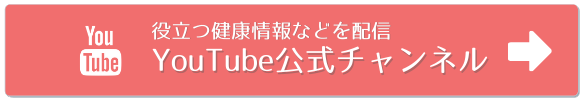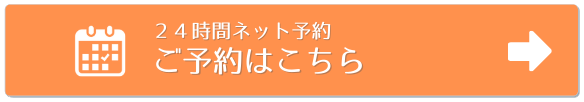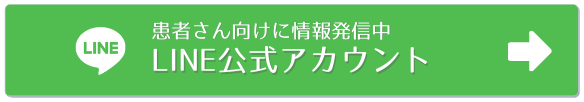目次
- ストレスで血糖値が上がる?糖尿病患者が知るべき対策3選
- ストレスで血糖値が上がる理由
- 慢性的なストレスと生活習慣
- ストレスがもたらす自律神経の乱れ
- ストレス対策3選
- ○○で脳のストレス反応を抑制
- 睡眠の質をUPして、ストレス改善効果UP
- 睡眠不足は脳や身体の疲労回復を妨げる
- 質の悪い睡眠が集中力・生産性を低下させてストレスに
- 睡眠不足が続くとストレスを感じやすくなる
- 良い睡眠の条件
- 睡眠時間が十分であること
- 毎日の就寝・起床時間が規則正しいこと
- 質の良い睡眠であること
- 睡眠の質を改善するための7つのポイント
- ポイント①適度な運動を行う
- ポイント②寝る前にスマホを使用しない
- ポイント③長時間の昼寝・寝だめをやめる
- ポイント④朝に太陽光を浴びる
- ポイント⑤就寝直前の飲食や飲酒は控える
- ポイント⑥朝食を抜かない
- ポイント⑦禁煙を行う
- 自分時間を作ろう!!
- ストレスコーピングの効果的な方法
- 環境を変えてみる
- 運動をする
- 休養をとる
- 趣味や娯楽をもつ
- 腹式呼吸をする
- 主治医や専門家に相談する
- まとめ
- YouTubeもおすすめ
- 気になる症状は当院へご相談を
- 参考文献・引用文献
ストレスで血糖値が上がる?糖尿病患者が知るべき対策3選
糖尿病や糖尿病予備軍の方は、血糖値や体重のコントロールが大切になってきますよね。
自宅での血糖値測定や病院での血液検査を行っていると思いますが、急に数値が不安定になり悩まれている方いませんか?
・仕事・家事・育児に忙しい
・家族が優先で自分のことは後回しにしている
・両親の介護を行っている
・睡眠時間が短く疲れがとれない

など忙しい生活を送っている方は、不安の解消、生活習慣の改善につながると思うので最後までご覧になっていただけたら嬉しいです。

こんにちは。
あまが台ファミリークリニック 管理栄養士の小笠原です。

血糖値が不安定になった
高血糖の状態が継続するようになった
食欲が急に抑えられなくなった

など、今までコントロールが安定していたのに急に血糖値や体重が不安定になることがありませんか?
実はその不安定の原因は、ストレスかもしれません!!
ストレスが原因で血糖値の上昇や不安定、体重の増加になることがあります。
今回は、ストレスが血糖値を上げる理由と対策を一緒に考えていきましょう!
ストレスで血糖値が上がる理由
厚生労働省の令和4年の労働安全衛生調査によると、仕事や職業生活に強いストレスを感じている方の割合は82.2%とされています。

多くの方が感じているストレスは、糖尿病とも深く関係しています。
こちらの研究は、29〜66歳のドイツ在住の労働者5,337人が参加して行われました。
調査開始時には参加者の全員が2型糖尿病を発症していなかったが、平均13年間の追跡期間中に約300人が新たに糖尿病と診断されました。
職場で過大な仕事を要求されて強いプレッシャーを感じている人では、そうでない人に比べ、2型糖尿病を発症するリスクが45%上昇することが明らかになりました。

肥満・年齢・性別などの要因の影響を取り除いて解析した後でも、仕事のストレスと糖尿病とは関連があることが示されました。
肥満のない人でも、ストレスが多いと糖尿病の発症率は上昇することがわかりました。
ストレスを放置していると、自分でも気がつかないうちに糖尿病のリスク・合併症の進行を高めてしまいます。
なにによってストレスを感じるのか、どんな反応が出るのかはその人の性格や世代、仕事環境や家庭環境などによって様々です。
ストレスとは心理学で利用されている言葉であり、精神面や身体面にかかる外部からの刺激に対して使われています。

ストレスの原因となる外部からの刺激をストレス刺激、ストレスによって心や体に起こる反応をストレス反応といいます。
ストレス反応は心理面や身体面、行動面に影響を及ぼします。
どの反応も放置すると、思いもよらない怪我や病気に繋がる可能性があります。

自分に起こっているストレス反応に早めに気がつき、対処していくのが重要です。
ストレスで血糖のコントロールが悪くなる理由は、ストレスによって血糖値を下げる機能が低下するためです。
ストレスが長期にわたって続くと、心や体に起こるストレス反応によってインスリンの働きが弱まり血糖値が上がります。
ストレスは、ホルモンの分泌に影響を与えます。
ストレスによって増加するホルモンはコルチゾールやグルカゴン、アドレナリンなどです。

血糖値を下げるホルモンがインスリンだけであるのに対し、これらのホルモンには血糖値を上げる作用があります。
なかでもコルチゾールは、肝臓で糖が作られるのを促す作用をもつホルモンです。
ストレスによって脳が刺激されると、コルチゾールが過剰に分泌されます。
過剰分泌されたコルチゾールによって、余分に糖がつくられてしまうため血糖値が高くなってしまいます。

ストレスを感じた時に、このような働きが起きてしまうため、血糖コントロールが悪くなり、高血糖の状態が起きてしまうのですね。
慢性的なストレスと生活習慣
慢性的なストレスはこのような行動を引き起こす可能性があります。
・睡眠不足
・食欲の増加(特に甘いものや脂っこいもの)
・運動不足
・アルコールの過剰摂取
・喫煙の量が増える

など、これらはすべて糖尿病の発症・悪化リスクを高める行動になってしまいます。
ストレスは、肥満のリスクを高めることも分かっています。
肥満は血糖値が常に高い状態になるので、糖尿病の原因の一つとされています。
ストレスによって肥満になるのは、自律神経の乱れによって全身の血流が悪くなったりホルモンの分泌量が減少したりして、基礎代謝が低下するためです。
基礎代謝が低下すると、脂肪の燃焼が悪くなります。

ストレスによって起こる食生活の乱れや運動不足も、肥満を引き起こす原因です。
肥満になると、内臓脂肪の蓄積によってインスリンの機能が低下し、血糖値を十分に下げられなくなります。
医学的根拠に基づいた「メディカルダイエット」。専門医による無料カウンセリングはこちらから。
また、*²喫煙は交感神経を刺激して血糖を上昇させるだけでなく、体内のインスリンの働きを妨げる作用があります。
そのため、たばこを吸うと糖尿病になるリスクが上がり、また合併症への進行を高めてしまいます。
日本人を対象としたある研究では、喫煙者は、非喫煙者と比べて、2型糖尿病を発症するリスクが38%高くなることが分かっています。
食べること・飲酒・喫煙でストレス発散をされる方は注意が必要かもしれませんね。
肥満は血糖コントロールをさらに悪化させます。
当院では肥満治療にも力を入れています。
医学的根拠に基づいた「メディカルダイエット」や、糖尿病専門外来について詳しくは
こちらのページ をご覧ください。
ストレスがもたらす自律神経の乱れ
ストレスが長期的に継続していくことで、自律神経の乱れも招いてしまいます。
自律神経が乱れると、胃腸の不調や睡眠障害が起き、生活リズムが崩れがちになります。
特に「交感神経」が優位な状態が続くと、インスリンの働きが弱くなり、糖の代謝がうまくいかなくなります。
自律神経の乱れから起こる精神的症状は、以下の通りです。
・うつ
・不眠
・だるさ(倦怠感)
・イライラする(神経質になる)

仕事や家事に集中できない場合や、他人のちょっとした発言に一喜一憂するなど、精神面でより負担を感じやすくなってしまいます。
ストレスが長期的に継続している状態が続き、自律神経が乱れ始めると、ますます身体的にも精神的にも大きな負担がかかりそうなことが分かりますね。

何がストレスになのか原因を考え、改善のためにどんなことができるか一緒に考えていきましょう!!
ストレス対策3選
○○で脳のストレス反応を抑制
*³プリンストン大学の研究チームはマウスを使った実験で、不安を制御する脳の領域が変化し、興奮を防ぐメカニズムが強化されることを突き止めました。
マウスを2つのグループに分け、不安を制御する脳領域である腹側海馬にどのような変化が起こるかを調べました。
GABAには、ストレスの緩和、疲労感の軽減などの効果があります。
このマウスは何のグループに分けられたと思いますか?
答えは
運動するグループと運動をしないグループになります。


運動は、脳が不安を引き起こす行動をコントロールする手助けになります。
不安・ストレスを抱える人にとっても、運動が効果的である可能性があります。
ウォーキングやヨガなど軽い運動を行ってみるのはいかがでしょうか?

でも、どのくらい運動すればいいの?
と疑問に思われる方もいますよね。
2023年に厚生労働省から「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」が発表されました。その中で、このような目安が出ています。
*⁴「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」

18歳から64歳までの方は、運動をはじめようと思ったとき、目安にしたい時間は「週60分以上」です。「1日10分×6回」でも「1日30分×2回」でも、好きな形で取り組んでOKです。

よく

「1回20分以上しないと効果がないのでは?」
といわれることがありますが、短い時間の積み重ねでも効果が期待できることがわかっているため、取り組みやすい方法で問題ありません。
運動の種類も何でもよいのですが、強度は「息が弾み汗をかく程度」が望ましいとされています。
速めのウォーキングや水泳、全身を使ったテレビゲーム、スポーツなど、取り組みやすいもので大丈夫です。
平日の朝や夕方、休日などに少しだけ時間を作って、カラダを動かす習慣をつけるようにしてみましょう。

ただし、運動習慣のない方は、急に激しい運動をはじめると、ケガなどのトラブルにつながる恐れがあります。
ストレッチや軽いウォーキングなど、負荷の軽い運動からはじめるようにしましょう。

ストレスの軽減プラスダイエット効果や数値の安定など、運動を行うことのメリットは様々ありますね。
睡眠の質をUPして、ストレス改善効果UP
脳や身体に蓄積された疲労を回復するためには、成長ホルモンを分泌させることがポイントになります。
その成長ホルモンは、どうすればしっかり分泌することができるのでしょうか?
それは、質の良い睡眠をとることです。

睡眠不足は脳や身体の疲労回復を妨げる
睡眠の役割のひとつは、脳や身体の疲労を回復することです。
活動した分しっかりと睡眠をとって回復することで、健やかな精神状態を維持することができます。
脳や身体に蓄積された疲労は、睡眠の際に多く分泌される成長ホルモンによって回復します。
また、就寝中は副交感神経が優位で、リラックスした状態になるのです。
睡眠不足は成長ホルモンの分泌に悪影響を与え、脳や身体の回復を妨げてしまいます。
慢性化すると疲労が蓄積し、精神的・身体的な不調を引き起こしやすくなるのです。

質の悪い睡眠が集中力・生産性を低下させてストレスに
ただ寝れば良いというわけではありません。「眠りが浅い」「寝ても疲れが取れない」と感じるような、質の悪い睡眠は集中力や生産性を低下させます。
よく眠れず、仕事が思うように進まない、ミスが続く、上司から叱責を受けるといった事態が続けば、精神的なストレスとなります。

睡眠不足が続くとストレスを感じやすくなる
睡眠不足は集中力・生産性を低下させるだけでなく、ストレスへの耐性も下げてしまいます。
また、ストレスは睡眠障害の一因にもなるため、睡眠不足とストレス、そしてメンタルヘルス不調は悪循環を引き起こしやすいです。
睡眠は怒りや悲しみといった、ネガティブな感情を整理するのにも必要なものです。
日中に悲しいことや辛いことがあっても、しっかりと睡眠をとることで寝ている間に感情を整理して、ストレスを和らげてくれます。
慢性的な睡眠不足は感情をネガティブな方向に誘導します。
そして不眠症などの睡眠障害は、うつや生活習慣病のリスクを増大させることも分かっているので、早期の発見と対処が非常に重要になります。

良い睡眠の条件
睡眠時間が十分であること
良い睡眠の条件の1つ目は「睡眠時間が十分であること」です。
しかし厚生労働省の調査によれば、男女20歳以上の約40%は「1日の睡眠時間が6時間未満である」と回答しており、慢性的に睡眠時間が足りていない人の数は決して少なくありません。
実際に必要な睡眠時間には個人差があるため、6時間未満の睡眠でも、業務に支障の出ない人もいます。
しかし、日中に眠気を感じることがあるのであれば、睡眠時間が不足している可能性が高いです。
仕事中のパフォーマンスを考慮しながら、睡眠時間を調整するよう心がけましょう。
毎日の就寝・起床時間が規則正しいこと
良い睡眠の条件の2つ目は「毎日の就寝・起床時間が規則正しいこと」です。
不規則な生活は睡眠時間が短くなりやすいだけでなく、体内時計のリズムが狂う原因にもなります。
たとえば、平日に不足しがちな睡眠時間を週末に取り戻そうとして長時間寝てしまうと、平日と週末の生活リズムに大きなズレが生じます。
結果的に「日中にだるさを感じる」「夜に眠れない」などの影響が出てしまうため、仕事が休みの日も生活リズムを大きく変えないことが重要です。

質の良い睡眠であること
良い睡眠の条件の3つ目は「質の良い睡眠であること」です。
質の良い睡眠について明確な定義があるわけではないのですが、
適度な長さで睡眠休養感があることが良い睡眠の目安ですが、昼間に生じる強い眠気や、睡眠中に目覚める回数なども、良い睡眠かどうかを判断する目安として役立ちます。』
と厚生労働省から説明されています。
たとえば、「十分な時間寝たはずなのに、疲れが残っている」という場合は、睡眠の質に問題があると考えられます。
睡眠の質を下げる可能性のある要因、睡眠の質を改善するための方法についてご紹介します。
睡眠の質を改善するための7つのポイント
睡眠の質を改善するためには次のようなポイントがあります。
ポイント①適度な運動を行う
「眠りが浅い」「寝付くまでに時間がかかる」という場合、習慣的に適度な運動を行うことも重要です。質の良い睡眠には強度が低く、一定時間継続できるウォーキング、サイクリングなどのような有酸素運動が良いといわれています。
大切なのは継続することなので、これらの有酸素運動を無理のない範囲で行いましょう。
ただし、強度の高い運動や就寝直前の運動は身体を興奮状態にし、寝付きにくくなってしまうため逆効果になります。

軽度な有酸素運動であっても、就寝から3時間前までを目安に済ませましょう。
就寝前の軽いストレッチやゆったりとした深い呼吸は、よい眠りの助けとなります。

ポイント②寝る前にスマホを使用しない
寝る前のスマートフォンやタブレットの使用が睡眠の質を下げるケースもあるので注意しましょう。
スムーズな入眠のためにはメラトニンの分泌が重要になりますが、就寝前にスマートフォンなどの強い光やブルーライトを浴びると、メラトニンの分泌が抑制されることが分かっています。
ベッドに入ってからは部屋を暗くし、すぐに眠れなくてもスマートフォンなどを操作しないようにしましょう。

ポイント③長時間の昼寝・寝だめをやめる
日中に眠気を感じる場合、短時間の昼寝が有効なケースもあります。
厚生労働省のWebサイトによれば基本的には15分程度、高齢者であれば30分程度が効果的な昼寝の時間だとされています。
適度な昼寝は日中の眠気を覚まし、睡眠の質の向上につながります。

また、寝だめも睡眠の質を下げる要因になります。
日常的に睡眠不足を感じている場合、週末に寝だめするのではなく、平日に十分な睡眠時間を確保できるように工夫しましょう。
平日と週末の起床・就寝時間の大きな差はソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ボケ)と呼ばれ、体内時計が狂う原因のひとつです。
ポイント④朝に太陽光を浴びる
人間の体内時計は24時間よりも少し長いため、毎日少しだけ体内時計を早め、24時間(1日分)の周期に調節する必要があります。
体内時計が調整されないと、就寝時間・起床時間が遅くなり、生活リズムがずれやすくなってしまいます。
体内時計の調整にとって重要なのが「朝に太陽光を浴びること」です。
太陽光には体内時計の周期を早め、睡眠に重要なメラトニンというホルモン分泌を促す効果があるので、朝起きたらカーテンを開け、太陽の光を浴びるようにしてください。

ポイント⑤就寝直前の飲食や飲酒は控える
就寝直前に食事や飲酒をすると、消化活動が活発なときに眠りにつくことになり、睡眠の質を下げてしまいます。
十分な量かつバランスの良い食事は健康維持に必要ですが、食事の時間にも注意してください。
できれば、夕食は寝る3時間前には済ませておきましょう。
加えて、寝る前のコーヒーや緑茶などのカフェインを含む飲み物、アルコール飲料の摂取も良くありません。
カフェインの覚醒作用は寝つきを悪くしますし、アルコールの摂取は眠りを浅くし、中途覚醒の原因になります。
飲酒によって眠気を誘われても、睡眠の質は落ちていることを覚えておいてください。

ポイント⑥朝食を抜かない
夜にしっかりと眠るためには、朝食を抜かないこともポイントになります。
朝食は日中に活動するためのエネルギー補給です。
朝食を抜くことで日中の活動量が落ち、夜間の睡眠に影響が出ることも考えられます。
また太陽の光と同様、規則正しい時間に朝食を取ることは体内時計の調整にもつながります。
朝食を食べない生活が常態化すると、体内時計が遅くなり、就寝時間・起床時間にも影響するため、できる限り食べる時間をつくるようにしてください。
ポイント⑦禁煙を行う
寝る前の食事や飲酒は良くないと説明しましたが、喫煙習慣のある方は、タバコが睡眠の質を下げている可能性もあります。
タバコにはニコチンなどの刺激物質が含まれるため、寝つきを悪くし、睡眠も浅くなりやすいです。
また、ニコチンは一定時間、血液中に成分が残ります。そのため、寝る直前の喫煙でなくても、タバコに含まれる成分が睡眠に影響する可能性はあります。
タバコは睡眠だけでなく、さまざまな健康リスクの増加につながるので、少しずつでも禁煙していくことが大切です。

*⁵
自分時間を作ろう!!
「運動も睡眠も良いことはわかっているけど…」
・忙しすぎて時間が作れない
・疲れすぎて、日々をこなすだけで精一杯
という方もいらっしゃると思います。
自分のことを後回しにして、家族のこと、仕事などを優先する優しくて一生懸命な方が多くいらっしゃいます。
そんな優しい方だからこそ、自分自身にも目を向けて優しく接してほしいのです。
・あなたが好きなことは何ですか?
・あなたが学生の頃に行っていたスポーツは?
・あなたの趣味は?
ここで1つご紹介したい考え方があります。
ストレスコーピングという考え方です。
ストレスコーピングとは、ストレスに対してうまく対処しようと意図的に行うセルフケアの1つです。

コーピング(coping)には、英語で「対処する・処理する」という意味があります。
ストレスコーピングを行うことでストレスを発散できたり、イライラしにくくなったりするのが特徴です。
ストレスに対してうまく向き合えるようになるため、ストレス対策として注目されています。
*⁶米国糖尿病学会(ADA)は、ストレスコーピングの効果的な方法として、次のことを提案しています。
ストレスコーピングの効果的な方法
環境を変えてみる
ストレスを感じることは、生活スタイルのどこかを変えた方が良いというサインである可能性があります。日課として繰り返しているパターンを部分的に見直してみることが解決の糸口になることがあります。
たとえば交通渋滞を逃れるために通勤ルートを変えてみるといったことでも効果があるかもしれません。
運動をする
運動は効果的なストレス解消法になります。運動を続けている人は、運動をあまりしない人に比べると、ストレスへの対応力があることが明らかになっています。
できる範囲内で良いので、運動を習慣としてはじめ、少しずつ運動量を増やしていきましょう。

休養をとる
心身の疲労や倦怠を感じた時には、無理をせずに十分な休養をとりましょう。食事の栄養バランスや毎日の適切な運動量などにも注意が必要です。
趣味や娯楽をもつ
日常的な仕事や家事、勉強から離れて、精神を爽快にリフレッシュするような自分だけの趣味・娯楽や気晴らしをみつけましょう。
腹式呼吸をする
ストレスがたまったときの対策として、リラックスできる時間を日常生活の中にもつことも大切です。
ゆっくりと腹式呼吸をする、ぼんやりと窓の外を眺める、森林浴をする、ガーデニングをはじめる、ゆったりお風呂に入る、軽く体をストレッチする、好きな音楽を聴くなど、気軽にできることをやってみましょう。

主治医や専門家に相談する
自分で対応しきれない大きな問題を抱えた時には、自分ひとりで解決するにはかなりの時間と労力を要することになります。
結果として心身の不調を招くことになりかねません。
そのような時には、信頼できる人や専門家に相談することが必要です。
「イライラすることが多くなってきた」
「憂うつ感が強くなってきた」
というのは
こころの不調としてのストレスのサインのひとつです。
そうしたサインが出ている場合は、症状を詳しく主治医に話しをしたり、療養指導士や医療スタッフなど相談しやすい人に相談したりする方法もあります。
また物事に神経質になりすぎず、80点主義で心の余裕を保つことも大切になります。
あなた自身がリフレッシュできる時間を10分だけでも作ってみることはいかがでしょうか?

家族や仕事も大切ですが、あなた自身を大切にしてみる時間を作ってみませんか?
まとめ
1.ストレスで血糖値が上がる理由
ストレスによって増加するホルモンには、3種類あります。これらのホルモンは、血糖値を上げる働きがあります。
2.慢性的なストレスと生活習慣
慢性的なストレスは、生活習慣と関連していて、糖尿病の発症や悪化のリスクを高めてしまう可能性があるので注意が必要です。
3.ストレスがもたらす自律神経の乱れ
ストレスが長期的に継続すると、自律神経が乱れてしまいます。交感神経が優位な状態が続くと、糖の代謝がスムーズにいかなくなるため、糖尿病の発症や悪化のリスクを高めてしまう可能性があります。
4.ストレス対策3選
運動を定期的に取り入れて、脳のストレス反応を抑制しよう
質の良い睡眠をとって、疲労回復・精神安定に努めよう
自分の時間を大切にしてリフレッシュしよう
今回は、ストレスと糖尿病の関係について一緒に考えてきました。
現代生活を送っているなかで、ストレスと生活を切り離すことは難しいことです。

大切なことは、そのストレスとどう向き合い、対処していくかになります。
ストレス軽減できる方法を見つけてみてはいかがでしょうか?
最後までご覧くださり、ありがとうございます。
YouTubeもおすすめ
当院 細田院長のブログやYouTubeも合わせて読んで頂くと、知識がますます深まるのでぜひご覧になってみてくださいね。
気になる症状は当院へご相談を
糖尿病や生活習慣病の予防は、早期の対応が重要です。
当院では、あなたの健康をサポートするために、最新の医療情報と親身な対応で、一人ひとりに合った予防策を提供しています。
単に病気の診断を行うだけでなく、生活習慣の見直しや、健康管理のアドバイスを通じて、患者様が健やかな生活を送れるようお手伝いします。
当院で提供している主なサービスには、以下のものがあります。
糖尿病予防
血糖値の安定をサポートする食事指導、運動療法を提案し、生活習慣病の予防を目指します。
定期的な健康チェック
血圧、血糖値、体重・腹部超音波検査などの健康チェック定期的を行い、早期の異常発見に努めます。
個別の栄養指導
一人ひとりのライフスタイルや健康状態、食習慣に合わせて、管理栄養士が丁寧に食事の内容を見直します。栄養バランスを整えるために、何をどのくらい食べればよいか、日々の食事に無理なく取り入れられる具体的なアドバイスを行います。例えば、「甘いものを控えたいけれどやめられない」「野菜が不足しがち」といった悩みにも、実践しやすい工夫をご提案します。

気になる症状がある方や、自分の状態を確認したい方は、ぜひ一度ご相談ください。
また、当院の糖尿病専門ページでは、より詳しい情報やよくあるご相談内容などもご覧いただけます。
👉 糖尿病特設サイトはこちら
疑問に思ったことや不安なことがありましたら、当院医師・スタッフにお気軽にお尋ねください。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。

参考文献・引用文献
令和4年 国民健康・栄養調査(結果の概要)
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001162830.pdf
厚生労働省 e-ヘルスネット「糖尿病」
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/metabolic/m-05-004.html
健康日本21(第二次)評価報告書
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kenkounippon21.html
国立国際医療研究センター 糖尿病情報センター
https://www.ncgm.go.jp/cgh/diabetes/
生活習慣病オンライン「糖尿病統計・調査」
https://seikatsusyukanbyo.com/statistics/disease/diabetes/
糖尿病ネットワーク「世界の糖尿病予測(IHME)」
https://dm-net.co.jp/calendar/2023/037633.php
*¹https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjbm/21/1/21_1500-3/_article/-char/ja/
Depression Is A Risk Factor For Type 2 Diabetes, Our Research Reveals (英国糖尿病学会 2023年9月7日)
New study reveals depression is a risk factor for type 2 diabetes (サリー大学 2023年9月7日)
*³Exercise reorganizes the brain to be more resilient to stress(プリンストン大学 2013年7月3日)
*⁴健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023-厚生労働省